| NO.106 |
第64回日本透析医学会学術集会・総会
札幌南一条病院
看護師 小山内 文哉氏
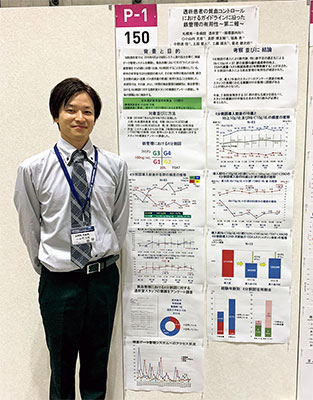
2019年6月28日から3日間、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で行われた「第64回日本透析医学会学術集会・総会」に参加しました。
私は本学会において「透析患者の貧血コントロールにおける鉄管理4分割図の有用性と課題」という演題で発表する機会を頂きました。
慢性腎臓病患者における腎性貧血は酸素運搬能の低下により臓器の虚血を進展させ、腎機能の更なる悪化、酸化ストレス増大とも関連し、心血管イベントの増加や生命予後にも悪影響を及ぼすことが示されています。したがって、腎性貧血の適正管理は臓器保護、QOLの保持、死亡リスクの低減にも繋がる重要な課題と考えられます。腎性貧血の主因はエリスロポエチンの産生低下にありますが、加えて鉄欠乏、慢性炎症、赤血球寿命の短縮、溶血などが関与するとされており、特に、鉄の適正管理は医療経済上も重要となります。
当院透析室ではシステム開発室の協力を得て、検査データ管理システムを構築し、慢性腎臓病患者の腎性貧血治療において血清フェリチン値・TSAT値による鉄管理を日本透析医学会(JSDT)ガイドラインに沿って4つの群に分類した4分割図を自動表示化することで、個々の患者さんの鉄の過不足、鉄利用の状態を早期に把握し、患者指導や治療方針の決定に活用してきました。
JSDTの慢性腎臓病患者の腎性貧血治療ガイドライン2015年版によると、鉄補充療法の開始基準はTSAT 20%未満かつ血清フェリチン値100 ng/mL未満が推奨されています。TSAT 20%、フェリチン100 ng/mLを境界とし、G1からG4の4つの群に分け、G1群(TSAT 20%未満かつ血清フェリチン値100 ng/mL未満)がG4群(TSAT 20%以上、かつ、血清フェリチン値100 ng/mL以上、300 ng/mL未満)で、かつ、鉄過剰の回避になることを目指して管理しています。
また、本研究ではヘモグロビン(Hb)の目標値を10g/dL以上とし、前述のシステム導入から2年間の貧血・鉄管理の推移とESAの使用状況、スタッフへのアンケート、システムへのアクセス数を調査・検討しました。研究の結果、4分割図の自動化の導入により、鉄代謝管理の適正化による鉄不足群の有意な減少、Hb<10g/dlかつ鉄不足群の目標Hb値の達成率の向上、ESAの減量・コスト削減、鉄過剰の回避の効果は2年間持続することが示され、4分割図の導入による腎性貧血管理の有用性が確認されました。
一方、スタッフへのアンケート調査・4分割図へのアクセス数の分析の結果、経験年数の短いスタッフでの4分割図への意識付けは持続していたのに対し、経験年数の長いスタッフでの長期にわたる意識付けの保持に課題があることが明らかになりました。
最後になりますが、本学会への参加にあたり研究開発調査助成を賜りました一般財団法人北海道心臓協会に深く感謝いたします。

