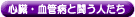| NO.6 |

北海道保健福祉部
部長 田村 正秀 さん
| 札幌市出身。昭和42年北大医学部大学院卒業、同51〜52年米国留学。同63年旭川医大第一外科助教授。平成4年美唄保健所長、同9年道保健福祉部長。 |
先生のご専門は何ですか?今までどんな研究をされたか併せてお答え下さい
心臓、血管など循環器疾患の診断、外科(手術)治療などの臨床に長年携わり、循環器、心臓血管外科などの専門医をしております。大学時代はさまざまな新しい治療方法、弱った心臓を機械で助ける補助循環、心筋保護、特殊な光を利用して患者さんの脳、心臓などの酸素不足(循環不全)を無侵襲で簡単に検出できる酸素モニターの開発などの研究に従事し、そのいくつかは今広く使われています。現在は行政医師として生活習慣病の対策など保健、予防、福祉の分野で「健康づくり」「生活の質向上」を目指して仕事をしているところです。北海適の心臓・血管病の現状をどう思いますか
この病気による死亡率は、残念ながら近畿地方とともに最も高いグループに入ります。全国的にみても北海道は、とくに都市部では食生活をふくめた生活習慣、ものの考え方?の欧米化が進んでおり、とくに冬季間は運動不足になるなど高血圧、心筋梗塞など動脈硬化性の心臓・血管病の多いのが特徴です。子供のころからの予防、「健康習慣」を身につけることが大切です。とくにこの病気の多い家族(高リスク集団)に対して徹底した生活習慣の改善、早期発見治療に努めることが必要です。また心臓・血管病は高齢化とともにますます増えてきます。治療についても高齢者、とくに後期高齢者個々人の「老化」の程度に合わせた治療法の研究がいっそう求められます。21世紀の医学医療は、どのようになるのでしょうか
社会の高齢化が進み動脈硬化、がんなど「生活習慣病」の克服が課題となります。予防医学、対策の重要性がますます高まるとともに、より有効、効率の高い「生活習慣の変容(よい方向にかえる)」研究が進みます。病気の治療は、治療後に障害を残さない「障害の医学」の方向に向かい、心臓・血管病でも生活の質、早い社会復帰を目指すことになります。痛い思いをする大手術は少なくなるでしょう。遺伝子治療の進歩により梗塞をおこした心筋に新しい血管(冠動脈)を再生させることや、動脈硬化そのものを防ぐことが可能になりそうです。心臓・血管病の予防についてのメッセージをお願いします
動脈硬化は無症状のうちに進行します。症状が出始めると完全に治すことは難しくなります。生活習慣病、自己責任の病気と言えます。予防にまさる治療法はありません。健康的な食事、運動、休養を柱に禁煙、節度ある飲酒など「健康習慣」を身につけ、自分の健康は自分で守ることです。「いまやセルフケアーの時代、自己責任による豊かな長寿を!」