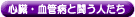| NO.4 |

旭川医大第一内科
教授 菊池 健次郎先生
| 小樽市出身。昭和42年札幌医大卒業。同42年同大第二内科入局。昭和56年同大第二内科講師。同57年同助教授、平成4年旭川医大第一内科教授。 |
先生のご専門を教えて下さい
私の専門は循環器内科です。肥満、高血圧・高血圧性心臓・血管病、脳血管障害、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、糖尿病などによる腎不全・動脈硬化性疾患といった生活習慣病、各種の心筋症、先天性心疾患、心臓弁膜症、およびこれらによる心不全や不整脈、また、透析患者さんの心臓・血管病などの成り立ちや診断、治療、予防に携わっています。北海道の心臓・血管病について先生のお考えは?
わが国では、高齢化社会と食習慣を含む生活様式の欧米化の進展に伴い、肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症、動脈硬化性心臓・血管病といった生活習慣病が増加しています。北海道も例外ではなく同様の傾向を示しています。21世紀の医療はどうなるでしょうか
「心臓,血管病」予防について道民の皆さんへのメッセージをお願いいたします高齢社会となり動脈硬化性心臓・血管病と、がんなどの悪性腫瘍(しゅよう)の増加が想定されます。したがって、小児期からの生活習慣の改善による心臓・血管病の予防についての啓蒙と患者さんや家族の心のケアーにも十分対応できる質の高い医療の提供、在宅医療・訪問看護の拡充とそれを可能にする制度の整備が強く求められます。
ライフスタイルの欧米化により、日本の学童の血中コレステロール値は欧米人のそれより高いことが指摘され、将来の心臓・血管病のさらなる増加が危倶(きぐ)されています。これを防止するためには、禁煙(若い女性の喫煙率の増加が心配)の徹底、運動の励行による運動不足の解消、獣肉など動物性の脂肪や蛋白質のとり過ぎの是正、適正化、和食の良さの見直し、肥満の予防と是正、食塩摂取量の減少(現在の1日12〜13gを10g以下にする)、アルコール飲量の適正化(1日ビール中瓶1本、日本酒1.5合、ウイスキー水割り1〜2杯のどれか1つ)など生活習慣病の促進因子の抑制を推進することが極めて大切となります。