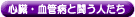| NO.2 |
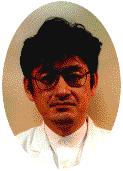
札幌医科大学医学部第2内科講師
三浦哲嗣さん
<第1回伊藤記念研究助成の対象となった先生のご研究は、どのようなものだったでしょうか。一般の方に分かりやすく説明ください>
心臓は全身に血液を送るポンプですが、心臓自身にも冠動脈という血管から血液が供給されています。この血液供給が十分でない場合に狭心症や心筋梗塞が生じます。
これらの病気の新しい治療法を開発するためのヒントとして注目されている現象にプレコンディショニング(注1)があります。これは、短時間だけ心臓への血液を減らした後に回復させる(例えば軽い狭心症のような状態で心臓を慣らしておく)と、心臓はより重篤な傷害である心筋梗塞に対して強くなるということです。このプレコンディショニングの仕組みに関する研究に対して伊藤記念研究助成をいただきました。
<その後、その研究はどのように発展したでしょうか>
初めは、ナトリウムイオン-カリウムイオンATPaseという細胞イオン輸送を調節する機構に注目していましたが、その後アデノシン(注2)とブラディキニン(注3)という物質がプレコンディショニングの際に心臓で産生されることが重要であること、またこのことを利用してジピリダモール(注4)やカプトプリル(注5)といった現在ほかの目的で使われている薬剤によりプレコンディショニングを増強できることもわかりました。
<心臓・血管病の恐ろしさが最近日本でもだいぶ理解されてきていますが、先生の今のご研究はどのような効果が期待されますか>
狭心症や、心筋梗塞に対しては既に優れた薬剤がありますが、いずれも基本的には心臓への血液供給がその需要に見合うようにするもので、プレコンディショニングのように心筋細胞そのものの抵抗性を高めるものではありません。
プレコンディショニングの仕組みを詳しく調べることを通して、心筋梗塞による傷害を心筋細胞のレベルで明らかにすることと、プレコンディショニングのように心臓を保護することのできる薬剤を見つけることを目標にしています。
<心臓・血管病の危険因子がわかってきました。一般の人が容易に取り組める効果的な予防対策を具体的に説明してください>
心臓・血管病の予防には高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満の予防と管理、適切な運動、禁煙が重要です。このうち高血圧、糖尿病、高脂血症は初期には自覚症状がはっきりしないことが多いですから、まず定期的な健康診断を受け、これらの問題点がないかどうかを調べる必要があります。
万歩計をつけて目標の歩数(例えば1日6,000〜8,000歩)歩くように日常生活を工夫すること、また毎朝排尿後に体重を測定する習慣をつけ標準体重に維持するように摂取カロリーを調整することは、目標とその成果が明らかになる有効な予防対策と思います。
<21世紀はもうすぐです。その前半の医療はどのように変わっているでしょうか。先生のご専門に関係した領域でよろしいですから近未来予測をしてみてください>
狭心症や心筋梗塞についても病態が細胞レベル、分子レベルで解明されて、新たな予防法、治療法が開発されて行くでしょうし、患者さんの病態を把握するための手段もさらに進歩すると思います。その結果、治療は現在にも増して個々の患者さんの病状に応じたものを多くの中から選択できるようになると思います。
<ありがとうございました>
注1 プレコンディショニング
プレ(pre 先行する)+コンディション(condition 条件付け)+ing
最近多くの研究者の関心を集めている現象。ごく短時間の心筋虚血がその後に起こる心筋梗塞の程度を軽くすることから、そのメカニズムを明らかにすることは心筋梗塞の新しい予防・治療の開発に役立つと考えられている。
↑戻る
注2 アデノシン(adenosine)
心筋細胞のエネルギー供給源であるATP(アデノシン三燐酸)の分解産物。酸素が不足すると増加する。
↑戻る
注3 ブラディキニン(bradykinin)
8個のアミノ酸からできているペプチド。痛みを起こす原因物質。強い血管拡張作用を持つ。酸素供給が絶たれると心臓に生じる。
↑戻る
注4 ジピリダモール 商品名ペルサンチン(日本ベーリンガー)
アデノシン分解酵素を阻害する。また、血小板凝集を抑制するので、血栓予防に用いられる。
↑戻る
注5 カプトプリル 商品名カプトプリル(三共)
降圧剤として用いられている。ブラシキニン産生を高める。
↑戻る