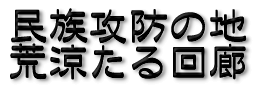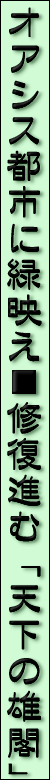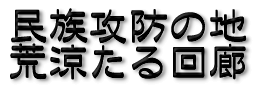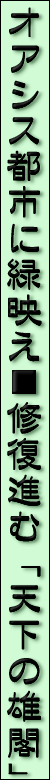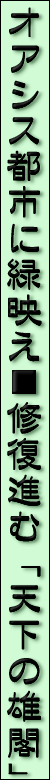 |
「有名な『馬踏飛燕』=『銅奔馬』とも。『白楊樹』参照=はこの部屋で見つかったのです。いま本物は蘭州の甘粛省博物館にあって、ここにあるのは複製ですが」
案内してくれた武威市外事弁公室の女性は甘粛省の至宝を語るとき、さすがに誇らしげな顔になった。
漢の武帝が渇望した汗血馬のブロンズ像「馬踏飛燕」が発見されたのは、ここ武威の雷台(れいたい)にある後漢時代の将軍の墓からだった。1969年、文化大革命を進めていた毛沢東の命令で防空ごうを掘っていて、漢墓が見つかった。
一日千里を走る汗血馬は天馬ともいう。躍進の象徴として実に格好の素材だ。人口30万人の武威市の中心、文化広場には86年に建てられた像がある。高さ16メートルのコンクリート製の基台の上に馬高3メートルのブロンズ像がのって、高々とそびえ立つ。泊まったホテル名も天馬賓館だった。
武威市外事弁公室が開いてくれた歓迎の宴でも、「『馬踏飛燕』は、いまの中国全体のシンボルマークでもあるんです」といった話が出た。
武威から張掖を抜けて酒泉に入った。オアシス都市が近くなると、鮮やかな緑が目立ってくる。祁連山脈の雪解け水が伏流水となり、あるいは川となって流れ下る恩恵だ。牧草地が広がり、ブドウ園がある。道路わきにもポプラの列が濃いシルエットを描き、北海道の風景を思わせてにわかに親近感がわいてくる。
酒泉の名の由来は、またしても漢代のヒーロー、将軍霍去病(かくきょへい)の故事にまつわる。匈奴を討った霍去病がこの地に至ると、武帝から褒美の酒が届いた。だが、全軍に分けるには足りない。そこで金泉という泉に酒を注ぐと、たちまち泉の水は酒に変わり尽きることがなかったという。
酒泉はまた、日本人に親しまれている「葡萄(ぶどう)の美酒 夜光の杯」の詩でもよく知られるが、それについては別の機会に紹介したい。
嘉峪関は酒泉から車で1時間、河西回廊の最も幅が狭い地(15キロ)に位置している。「天下の雄閣」の名があるとおり、堅固、勇壮な姿は大切な観光資源である。1985年にトウ小平の指示で700万元(1元は約15円)をかけて城楼復元など大修復工事が行われ、私たちが訪れた時もあちらこちらが工事中だった。
三つある城楼のうち開放されているのは一つだけだったのだが、写真撮影の関係でどうしてもほかの楼にも登りたかった。監視の若い兵士は「規則だから」と気の毒そうに首を横に振るばかりだったが、ガイド役の蒋さんが粘って主任を引っ張り出してくれた。
「上に知れたら首になる」。主任は土臭く日焼けした顔をほころばせ、快く許可してくれた。こちらが謝礼のつもりで差し出した日本からの土産を絶対に受け取ろうとしなかった。
同行した蘭州市人民政府派遣の通訳・王臨川さんがしきりに感嘆の言葉をもらした。「あの主任はいい人です。いまの中国人は20年前と違って『財迷(ツァイミー=守銭奴)』ばかりで、こんなときはお金を要求する人が多いんだけれど」
城楼に登って眺めれば、西に向かって長城が竜のようにくねって伸びている。現在、北京近郊の八達嶺(はったつれい)などに残る長城と違って、低い土塀のような感じで干しれんがの壁が続く。
明の時代はこの嘉峪関までが勢力範囲で、その先は異民族に征服されていた。当時、関の守備についていた常駐の兵士は数百人という。最前線に立つ兵の心は敦煌に向かっていたのか、遠く離れた故郷を思っていたのか。
|
 |
| 現在は製鉄の町である嘉峪関の市街では製鉄労働者が路上将棋に夢中になっていた。「象棋」という。日本の将棋にも西洋のチェスにも似ている |
 |
| 「蘭州あての荷物あり」と段ボールに書いて、空トラックが通るのを待つ回族の男性。荷物のヒッチハイクだ=嘉峪関付近の国道 |
|