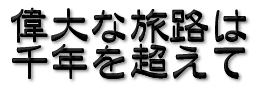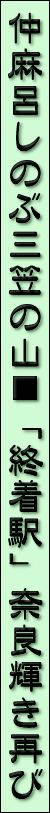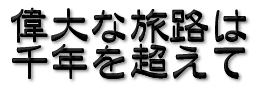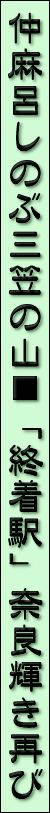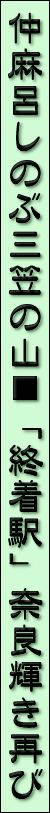 |
復元が進む平城宮跡に立って東を見やると、奈良市街に接して緑の山並みが望める。
鑑真の同時代人として、唐の国からこの山をはるかに望む日本人がいた。716年に遣唐留学生に選ばれて渡航し、玄宗皇帝の厚い信任を受けて高級官僚となっていた阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)、中国名・晁衡(ちょうこう)である。
仲麻呂は帰国を許され、鑑真が加わったのと同じ遣唐使の帰国船団に参加した。ところが、鑑真の船は日本にたどり着くが、仲麻呂の船は南に流され、帰国の夢は果たせずに終わる。再び唐に仕えた仲麻呂は、安南節度使という現在のベトナムに当たる地域の長官などを務め、770年に長安に没した。
唐に住むこと実に半世紀を超えた。
難破する直前、帰国を控えた高ぶりを胸に仲麻呂は詠じた。
天の原ふりさけみれば春日なる
三笠の山に出でし月かも
三笠の山とは、山焼きで有名な若草山のすぐ南、春日神社の奥に広がる御蓋(みかさ)山をさす。
芭蕉が異国から訪れた鑑真に句をささげたのと同様に、仲麻呂をうたった詩人が唐にいた。李白である。
日本の晁衡帝都を辞し
征帆一片蓬壺(ほうこ)をめぐる
明月帰らず碧海(へきかい)に沈み
白雲愁色蒼梧(そうご)に満つ
(晁衡は長安を去り、船は日本に向かったとばかり思っていた。それなのに、明月=晁衡は緑の海に沈んでしまった。悲しみが青い空を覆っている)
李白は「仲麻呂遭難」の報に接し、てっきり死亡したものと思い込み、追悼の思いを歌ったのだ。
仲麻呂は李白、王維ら超一流の詩人、文化人と交流を重ねた。ペルシャ系の美女「胡姫(こき)」がいる酒場で、シルクロードを西から渡ってきた青い目のお雇い外人官僚と酒を飲みながら語り合ったことだろう。あるいは玄宗のわきに寄り添う楊貴妃とも言葉を交わしたかもしれない。国際都市・長安のきらめくばかりの繁栄ぶりがしのばれる。
鑑真が没した奈良、仲麻呂が眠る長安=陝西省西安。現在、両市は友好都市として交流を続ける。西安市内にある玄宗皇帝の離宮・興慶宮の跡には仲麻呂の立派な記念碑が立てられ、側面には仲麻呂の望郷の歌が中国語で彫り込まれている。
長安とのつながりは、さらに西の世界との交流の豊かなあかしを奈良にのこす。
東大寺の北側に静かなたたずまいをみせる正倉院−。8世紀半ばに造営されたこの倉の宝物の一つ「金銅八曲長杯」は、ペルシャに起源を持つデザインとされる。これとまったく同じ形の「白玉刻花八曲長杯」(唐代、西安市出土)がいま札幌・道立近代美術館で開催中のシルクロード展に展示されている。
正倉院には、二こぶのラクダにまたがる楽人を鮮明に描いた琵琶もある。私たちが実際に歩いたタクラマカン砂漠周辺のオアシスを連想させる異国情緒あふれる優品だ。透明なガラス器ははるか西のローマ・地中海世界の香りを漂わす。聖武上皇の遺品をはじめとする正倉院の宝物は染織品の断片を含めれば数万点にも上り、その整理作業はいまも続いている。
古都・奈良は確かに「シルクロードの終着駅」であり、その歴史と現在を確かめるために訪れる人はきょうも絶えない。
|
|