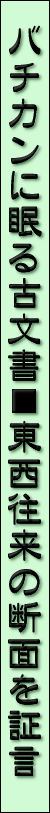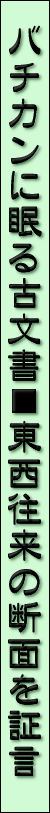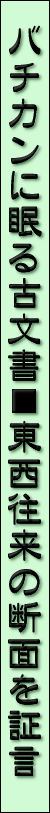 |
マルコ・ポーロたちが4半世紀におよぶ大旅行に費やした時期は、日本では鎌倉時代に当たる。ちょうどモンゴルの元軍が2度にわたって来襲したころだ。日本武士団は健闘し、台風も重なり、元軍の撃退に成功した。
攻撃を受けた日本から見ると意外なことなのだが、マルコはこの恐るべきモンゴルのひ護のもとに、ヨーロッパからアジア大陸の東の果てまでを歩いていた。3人の大旅行の前に、すでにマルコの父と叔父は中国を訪ね、フビライの厚い信任を得ていたのだ。
モンゴル帝国は東アジアはもちろん、中央アジア、西アジアのほぼ全域を支配下におき、東ヨーロッパにまで迫ることもあった。抵抗する敵は徹底的に虐殺し、略奪する遊牧民族ならではの激烈な遠征の結果だったが、征服後には大陸に「モンゴルの平和=パックス・モンゴリカ」を現出させた。
宮廷には西方の異国の人々「色目人」が積極的に登用された。一定距離ごとに馬をおいた駅逓が置かれ、通行証があれば旅人の安全は確保された。マルコたちは当時の地球上で最強の権力者のお墨付きを持ち、空前の“大陸間ハイウエー”を往復したことになる。北京のマルコはフビライの寵臣(ちょうしん)となり、しばしば特命を受けて国内を視察したという。
マルコの大旅行に先立つもう一つの大陸横断の記録を見るために、私たちはローマにあるカトリックの総本山バチカン(ローマ法王庁)の公文書館を訪ねた。世界各国からの観光客でにぎわうサン・ピエトロ広場の北側にバチカンの諸官庁が並ぶ。日本のカトリック協議会事務局ローマ駐在員事務所長を務めるレイモンド・レンソン司祭の案内で公文書館に入った。
目的の文書は、1246年にモンゴル帝国の第3代君主であるグユク・ハーンがローマ法王イノケンチウス4世にあてた手紙である。モンゴルのヨーロッパ侵攻に危機感を募らせた法王は、攻撃をやめるよう求める文書を修道士プラノ・カルピニに託してモンゴルに派遣した。これに対する返書が公文書館にある。東西交渉史を学ぶうえでかけがえのない貴重なこの文書を、公文書館は快く閲覧させてくれた。
1920年にバチカンで発見されたという返書は、薄い赤箱に収められ、虫食いひとつなく、完ぺきな状態で保管されている。グユクはこの返書のなかで、法王の要求を聞くどころか逆に臣下になるよう命じる強硬な姿勢を示している。ペルシャ語の筆跡はグユクの自信を示すかのように明せきだ。2カ所に押された約20センチ四方の巨大な印章に気おされる。
モンゴルは権力継承問題などもあり、その後ヨーロッパには攻め込まなかった。カルピニのもたらした返書は厳しい文面とは裏腹に、ヨーロッパの一修道士が2年ほどでアジアとの間を安全に往復できた事実を伝える。
この文書はヨーロッパ人が初めて目にした「紙」の一つだったといわれる。約1900年前に中国の蔡倫が確立した製紙法がまず西方に伝わったのは、751年に唐とイスラム勢力のアッバース朝が現在のキルギスタンのタラスで会戦し、敗北した唐軍のなかの紙すき職人が捕虜になったことによるとされる。軽くしなやかな紙を作る技術は、主にイスラム世界を経由してそこからゆっくりと西進し、13世紀ごろに西ヨーロッパに伝わったという。
紀元前の時代からローマの市民は東方の国の絹の存在を知っていた。東の中国の人々もはるか西に強力な異国があることに気付いていた。時代も空間も民族の違いも超えて人々は行き来した。そのあかしともいえる一枚の古文書を目の当たりにし、私たちは深い感動に包まれた。「すごい文書を見ることができましたね」。バチカンに日ごろ出入りしているレンソン司祭も少し興奮気味だった。
公文書館を出ると、突然土砂降りの雨が襲ってきた。振り返れば、シルクロードを中国から西へ西へとたどる旅はひたすら乾燥地帯を歩く旅だった。だから、傘を持つことはまったくなかった。ずぶぬれになりながら、私たちは旅の終わりを実感した。
|
|