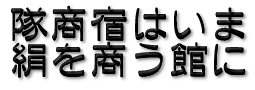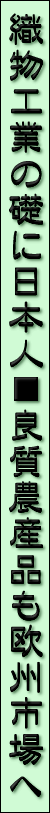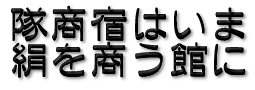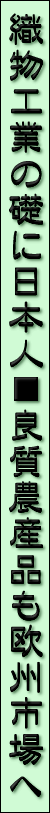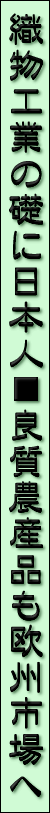 |
イエットキルさんの案内でブルサ郊外のイルマジペック繊維会社を訪ねた。二代目経営者のドガン・イルマジペックさん(70)の名刺には「1930年創業」と書かれている。ブルサでも有数のしにせ企業だ。工場は従業員45人と大きくはないが、高品質の絹の生地を生産することで知られている。
原料の生糸は地元産もあるが、大半はイタリアから輸入し、製品もまたイタリアに輸出する。そのイタリアは中国やブラジルから生糸を輸入しているという。国際貿易の複雑な網の目のなかでトルコを代表する絹製品が作られていることがわかった。「日本のシルクはすばらしいですね」。客人の国の絹をたたえるイルマジペックさんの控えめな笑顔が印象に残った。
イルマジペックさんの父親が創業したちょうどそのころ、このブルサの絹織物工業の近代化に深くかかわった日本人がいた。浄土真宗本願寺派(西本願寺)の第22代法主を務め、中国新疆などに探検隊を派遣し、仏教遺跡の発掘・調査に精力的に取り組んだあの大谷光瑞(こうずい、1876−1948年)である。
大谷は初代大統領ケマル・アタチュルクのトルコ革命に強い共感を寄せた。武器を供与したとの説まである。その近代化政策支援の一環として1928年にトルコを訪問した際、ブルサに絹織物の合弁会社を設立した。この企業はまもなく倒産したが、工場にはアタチュルクも視察に訪れたという。
破天荒な宗教指導者として知られる大谷だった。それにしても欧州列強の探検隊に対抗するシルクロード探検といい、このブルサでの事業といい、いったいなにが当時の日本人としてはケタ違いの大事業に彼をかりたてたのだろう。正確な事情は明らかではないが、新疆もトルコもロシア=ソ連と接する地政学的に重要な地域であったことにカギがあるのかもしれない。
私たちが中国のシルクロードで干しブドウの取材をしたことを伝え聞いて、ブルサの200キロ南西にあるイズミールの街から「ぜひ、われわれの商品も見てほしい」という熱心な要望が寄せられた。誘いの主は「タリッシュ」という農業協同組合の連合組織だった。農協連合という言葉にひかれ、私たちはブルサをあとにし、エーゲ海に臨むイズミールに向かった。
「タリッシュは125,000人の農業生産者、128の農業協同組合で組織されています」。イズミールに着くと、輸出部門の責任者フスヌ・サルペルさんが説明してくれた。現在、干しイチジク、干しブドウ、オリーブ油、綿花の販売輸出が事業の柱になっているという。
干しブドウ工場を見た。生産者がすでに乾燥を終えたブドウを持ち込む。工場でいったい何をするのかと思ったら、ひたすら洗浄と選別を繰り返す作業だった。工程に沿って3棟の工場を回り、そのたびに手洗いと靴の消毒をさせられるのには驚いた。最後の工程は女性従業員によるなんと手作業の全商品検査だった。
「欧州連合(EU)の検査員がいつ来ても大丈夫。品質管理には絶対の自信があります」。主要市場としての欧州をみつめる視線は熱い。日本には輸出していない。「ぜひ市場として開拓したいのだが、商談はなかなか進まない」と、サルペルさんはちょっと残念そうだった。
翌日、イズミールの南の郊外にあるエフェスの古代都市遺跡に足を運んだ。3,000年以上も前にイオニア人による建設が始まり、後にローマ領となった「世界の七不思議」に数えられた遺跡である。
このエフェスで西暦431年にキリスト教の会議が開かれ、ネストリウス派が異端と断罪された。以後、ネストリウス派は東方への布教に努める。その足跡は唐代の中国にまで及び、「景教」として信仰されたことは、いま札幌・道立近代美術館に拓本が展示されている781年建立の「大秦景教流行中国碑」によって明らかである。
エフェスには24,000収容の大劇場跡が残る。全66段のその高みに立てば、眼下にエーゲ海が広がる。シルクロードの終着であり起点でもあるローマはもう指呼の間にある。
|
|