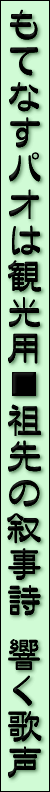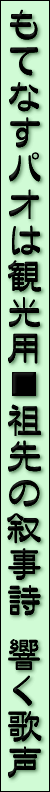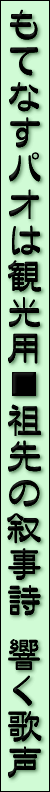 |
フフホト市の郊外に、観光と牧畜を兼業するモンゴル人一家を訪れた。観光用に用意されたパオ(天幕)に案内され、食事が始まった。
乳白色の馬乳酒(マーネイチュウ)はアルコール度が12%。少し酸っぱくて口あたりがいい。酒のさかなに米や小麦粉を羊油で揚げた物、漢語では酪や醍醐(だいご)とでも記すのかチーズやバター、ヨーグルトに似た乳製品をつついているうちに、羊1頭を料理したメーンディッシュが運ばれてきた。羊の骨つき肉の大きなかたまり、レバーその他の内臓を焼いたり、いためたのがたっぷり出た。岩塩や羊の乳のソースをつけて食べる。野趣豊かでうまい。
それまで農夫農婦然として立ち働いていた夫婦が、美しく着飾って登場した。バガナさん(37)夫妻だ。歓迎の歌を次々に歌い、酒を勧める。酒を敬う歌、酒を飲んで牛にも馬にも負けない力をつける歌、草原は私のふるさとだ、という歌…。
モンゴル族の楽器として日本でもなじみ深いのは民話『スーホーの白い馬』で知られる二弦琴の馬頭琴だが、モンゴル音楽の典型は声による音楽、つまり歌にある。雄大な自然をうたい、祖先の叙事詩をうたい、男女の愛情をうたう。裏声や、ソプラノ・バス両方を駆使するホーミーの技法も伝承されている。夫妻の歌も、草原の民にふさわしい迫力があった。
バガナさんの一家は両親と子供2人の6人家族。羊は約300頭飼っていて中堅どころといえる。バガナさんの父親タラさん(70)の話を聞いた。「私の父が生まれた時、もうパオには住んでいなかったそうです。野菜を初めて見たのは14歳の時だった。ニガウリです。果物も若い時はなかったよ。そのころ羊は600頭ぐらいいて、いまは半分になったけど、いまのほうがずうっと暮らしいい」
モンゴル高原は、現在のモンゴル人民共和国と内モンゴル自治区のほぼ全域をおおう標高1,000メートルから2,000メートル前後の高地である。寒暖の差が激しい大陸性気候の乾燥地帯だ。この高原に紀元前以来、匈奴(きょうど)、突厥(とっけつ)、契丹(きったん)、ウイグルなどトルコ系やモンゴル系の遊牧諸民族が興亡を重ねてきた。
世界史の上ではとかく北辺のわき役としてしか見られてこなかったこれら遊牧民族の一つであるモンゴル族が、突然巨大なエネルギーを発揮して世界最大の大帝国を建設したのは13世紀だった。チンギスハーンとその子孫による征服は、西はロシアからイラン、イラク、小アジア、南はミャンマー、ベトナム、東は朝鮮半島にまで及んだ。
広大な版図のなかに多数の異民族を包含する統一が生まれたことによって、東西の交通路は一段と開拓され、マルコポーロら多くの旅行家が西から東に向かった。サマルカンドなど中央アジアや西アジアの各地から各種工芸技術者が集団でモンゴル本土や中国に移住した。イランのコバルト顔料が中国の磁器と結び付いた染め付けの技法が生まれたのもこの時期だ。西と東がこれほど強く結び付く歴史はそれまでなかったと言える。
大モンゴルの繁栄は、帝国の中核をなす元朝が14世紀後半に滅びるとともに幕を下ろし、モンゴル族は再びモンゴル高原に引きこもった。第二次世界大戦後、外モンゴルは旧ソ連の後押しで独立に成功したが、内モンゴルは中国内にとどまり現在に至る。
夜、フフホト市の中心部で開かれる大バザールをのぞいた。サッカー場ほどもある広場に畳1、2枚の大きさの敷物に品物を並べる店が数百店。古本、ミニチュアカー、衣料品、背筋力テスト、カラオケは28台。酔っ払いは1人もいず、家族連れがなごやかに夜の散歩を楽しんでいた。
|
|