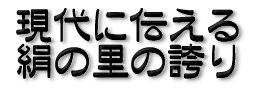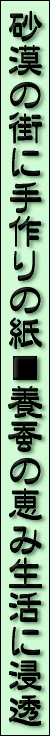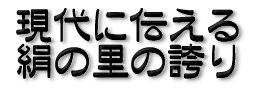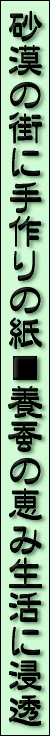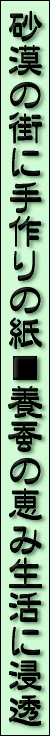 |
「絹の里」の誇りを傷つけるわけではないが、養蚕はホータンで生まれたものではないらしい。そのことを示唆した偉人がいる。7世紀、インドから仏教経典を持ち帰る途中にホータンに立ち寄った玄奘(げんじょう)である。シルクロードのいたるところで実に頻繁に登場する人物だ。
かれの見聞を弟子がまとめた地理書『大唐西域記』は、玄奘が聞いたホータンの伝説をこう記す。
昔この国には桑の木も蚕もなかった。そこで王は東方の国に縁組を申し込み、嫁入りする女性に桑の種と蚕を持参するよう頼んだ。女性は帽子に桑の種子と蚕を隠し、関所を抜けてやってきた−。
玄奘から1,200年後、新疆を考古学調査した英国のオーレル・スタインはホータンに近いダンダン・ウィリク遺跡で一枚の板絵を発掘する。この伝説を描いたものだった。玄奘の記録をスタインが補強したことになる。
ホータンは19世紀末から今世紀初めにかけ、列強による新疆探検の最前線だった。野心あふれる探検家の双璧(そうへき)は、スウェーデンの地理学者スウェン・ヘディンであり、英国のスタインだった。ヘディンはシルクロードの名付け親リヒトホーフェンの弟子である。死を賭したタクラマカン砂漠探検で勇名をはせ、楼蘭の遺跡を発掘した。
ヘディンは楼蘭で約2,000年前の漢代の絹を掘り出し、スタインはホータンに近い砂漠のニヤ遺跡で立ち枯れた桑の大木をみつけた。いずれも、かなり早い時期にこの砂漠周辺に東から絹が運ばれ、養蚕が伝わっていたことを示す成果だった。
ホータン地区政府のマイティヌールさんが「手作りの紙を見ませんか」と、マイスさん(54)の家に案内してくれた。
原料はなんと桑の木の皮だった。これを水に浸し、あくを加えて煮たうえで木づちでたたく。ぬめりが出たところで水で薄め、どろっとした液体を木枠に流し込めば、たちまち乾いて桑紙のできあがりだ。魔法を見るような手際のよさ。この紙は水分をよく吸収するので、ウイグル帽のしん材や薬の包装紙に使われるという。
和紙原料の楮(こうぞ)はクワ科だから不思議ではないのだが、絹のまちの桑紙とは、なんとも心憎い符合ではないか。
紙といえば、高句麗出身の唐代の武将・高仙芝を思い出す。パミール高原のダルコット峠を果敢に越えてチベット系王国を滅ぼし、歴史に名を残した高仙芝は、この大手柄のあと、751年にタラスの戦いでイスラム軍に敗れた。このとき捕虜になった唐の製紙職人がイスラム世界に製紙技術を伝え、それがさらに欧州に広がったとされている。高仙芝の幕僚を務めた岑参(しんじん)は、西域各地を歩いてうたい、「辺塞(へんさい)詩人」として名高い。西域と紙との因縁は深い。
ウイグル族の農家も訪ねてみた。庭にはブドウ棚が涼しげな日陰を作り、下の縁台に男の赤ちゃんが寝かされていた。木製の揺りかごに布できつく固定されている。かわいいおちんちんが中央の木管に差し込まれている。おしっこが自然に下に流れる仕組みだ。
この揺りかごはキルギス、ハザク(カザフ)などウイグルと同じトルコ系民族に共通するものらしい。もちろん、女児の場合はどうするかを母親に聞いた。しかし、ウイグル語→漢語→日本語への翻訳の過程でわけがわからなくなってしまった。
土造りの屋内に入ると、ブドウ棚の下よりさらに涼しく心地よい。羊肉入りのいためご飯とともに桑の実が供された。意外にも冷蔵庫があるらしく、冷たい。しかも甘い。砂漠のほとりに、こんなにみずみずしい食物があったとは。
深い歴史を宿し、玉と絹を生むホータンは、旅人にやさしい実り豊かなまちである。
|
|