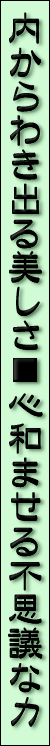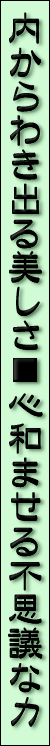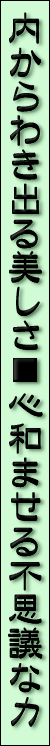 |
6月初め、タクラマカン砂漠の南縁を走る西域南道には砂嵐が吹き荒れていた。私たちは朝早くカシュガルを四輪駆動車でたち、10時間かけて500キロを走り抜け、全身砂まみれでホータンにたどり着いた。
ホータン地区政府のハジ・マイティヌールさん(47)が笑顔で迎えてくれた。ウイグル族のイスラム教徒だ。「ハジ」は聖地メッカに巡礼したことを示す。社会主義国の中国でもメッカ巡礼団が組織されている。「1986年の団の引率員を務めました」と誇らしげに自己紹介した。
玉の取材の手配を頼むと、「玉は南の崑崙(こんろん)山脈から雪解け水とともに流れてくる。いま川に水はない。だから玉もない。また秋に来てください」と、にべもない。雪解けは始まっていると思ったのだが、早過ぎた。
1900年も前に書かれた『漢書』西域伝には、于◆(うてん=ホータンの旧名)の項に「玉を多く産する」とある。7世紀にここに滞在した唐僧の玄奘も玉に言及し、13世紀に南道を東に向かったマルコ・ポーロも『東方見聞録』でホータン周辺の玉について触れた。玉と聞けば中国の人々が反射的にホータンを連想するのは、こうした歴史的な裏付けがあるからだ。
市街地の加工・即売所には、日本円換算で数百円の庶民向けのピアス、指輪から数百万円もする工芸品までが無数に並ぶ。
ウイグル族の女性幹部職員ルキアさん(25)が一つの作品を指さした。「これが最高級の白玉です。私たちは羊脂玉と呼びます」。内側からにじみ出る美しさが玉の身上だ。それを「羊のあぶら」と表現する。なんとなくわかる感じもするが、ちょっと生々し過ぎるようにも思う。
マイティヌールさんが夕食時にこぶしほどの大きさの白玉の原石を持ってきてくれた。「玉磨かざれば光なし」の通り、輝きはない。握ると、どきっとするほど冷たい。きめ細かな表面の触感は心地よく、しだいに体温を吸収してぬくもりをたたえる。心を和ませる力がある、そんな感じがした。
夕食には地区文物管理所の若手研究員や運転手さんも加わった。一人が「一昨年、二人の農民が60万元(約840万円)の大きな玉をみつけた」と切り出した。こうなると、もう止まらない。「でも、いい玉を発見したことがわかると国に没収されるらしい」「上流ほど良質で大きな玉がある」「無理に急流を上り詰め、崑崙の山から帰らなかった男もいる」−。みんなが陶然として採玉譚(たん)を続ける。どこまでが本当で、どこからが作り話なのかわからない。これがホータンの人々にとっての玉なのだろう。
翌日、于◆の都跡とされるヨトカン遺跡を訪ねた。西暦399年に長安をたってインドに向かった僧・法顕(ほっけん)はここに立ち寄り、「僧は数万」と記録した。二百数十年後の玄奘は「僧徒五千余」と書いた。西域きっての大仏教王国だったのだが、いまは廃屋一つなく、綿花畑だけが広がる。
近くに住むウイグル農民が、土にまみれたつぼを手にしてやってきた。私たちに同行している新疆文物考古研究所のゼパールさん(24)が「本物だ。1000年以上前のものだろう。二級文物クラスかな」と、こともなげに鑑定する。立派な文化財だ。畑を少し掘ればいくらでも出てくるという。
ヨトカンが栄えたころ、この地域の住民の主体はペルシャ系の人々だった。現在のトルコ系のウイグル族が移ってきたのは10世紀を過ぎたころらしい。古い都は滅び、仏教も消え、住民も変わった。しかし、ホータンの玉と、それに寄せる人々の思いは時代と民族を超えて健在である。
(注)◆は「もんがまえ」に「眞」
|
|