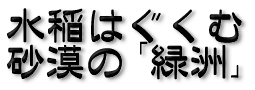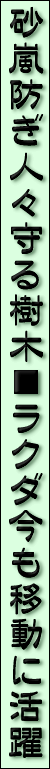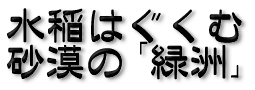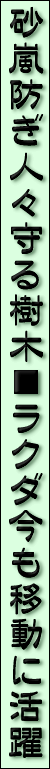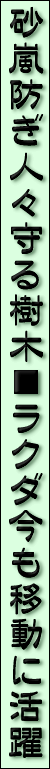 |
オアシスはあくまでも「島」に過ぎない。そこを一歩出れば乾燥の大海が広がる。この区切りは明確だ。川か人工的水路が途切れれば、もう土と小石のゴビ灘(たん)か、砂だけの砂漠になる。ごく一部の草が生えるだけで樹木はまったくなくなる。
カシュガルを出て、ホータンに向かう途中の西域南道で砂漠の強烈なパンチをくらった。小さなオアシスの集落を抜けたとたん、砂嵐(あらし)が襲ってきたのだ。
アッという間に視界は50メートルほどに落ち込む。走行を続けるのは危険なので、路肩に車を止めた。車体を砂粒が音をたててこすってゆく。驚いたことに、この砂嵐のなかを平然とロバにまたがって動いているウイグル族がいる。目や肺の中はいったいどうなっているのだろう。
風が弱まるのを待ってゆっくりと動き出し、次のオアシスに滑り込むと、さきほどまでの砂嵐がうそのように収まった。いや、収まってはいないのだが、オアシスの木々が砂を防いでいるのだ。その証拠に、上空には黄色い砂が大きく舞っている。ここでもオアシスの力に感動してしまった。
砂漠そのものに人が住むことはできない。ゴビ灘に暮らすのも難しい。しかし、新疆では砂漠やゴビ灘に接して多くの人々が生きてきた。
カシュガルから南のパキスタンに抜ける道路を中国では「中巴(パ)公路」と呼ぶ。標高3,000メートルを超えるパミール高原のこの公路を走っているとき、ラクダにまたがって移動する牧畜民を追い抜いた。放牧されたラクダの群れはしばしば見かけたが、実際にまたがっている人物と会ったのは初めてだ。あわてて車をバックさせ、話を聞いた。
この人はイラン系のタジク族で、ハゲッキさん(30)といった。周囲は砂漠ではないが、乾燥しきった土の原が続く。ハゲッキさんはパミール高原の高峰ムスターグ・アタ(標高7,546メートル)のふもとにある夏の牧場の天幕から川の近くにある土作りの居に移動する途中だった。
ラクダの二こぶの間に荷物を振り分けている。中身は夏の牧場で拾い集めた羊のふんで、住まいでの燃料にするという。「だいたい一頭が250キロの荷物を運べる。牧場から家まで約40キロ、ちょうど一日の行程だ」と教えてくれた
。
中巴公路は舗装され、貨物輸送の主体はかつてのラクダの隊商からトラックに変わった。長距離旅行の人々はバスを使う。ラクダは減った。しかし、自動車を持たない牧畜民が牧場を行き来する手段として、ラクダはいまも重要な役割を果たしている。
ラクダといえば「砂漠の船」などといわれ、すぐに砂漠を連想する。しかし、現在では活躍の実際の舞台は砂漠ではなく、ハゲッキさんたちが暮らすようなゴビ灘が多い。ただ、いまも砂漠でラクダが大活躍する数少ない場面がある。
ウルムチに本部を置く新疆文物考古研究所のウイグル族のイディリス副所長によると、研究所の調査隊がタクラマカン砂漠の古代遺跡発掘に向かうのにしばしばラクダを使う。砂漠では石油採掘が行われており、ドイツ製の砂漠専用車を石油会社から借り上げることも可能だが、たいへんなカネがかかる。どこでも飼われているラクダは最も手軽で確実な足になる。イディリスさんは「本当にラクダは乾燥に強い。一週間近く水をやらなくても歩いてくれる」と頼もしそうに話した。
イディリスさんの好意で、国内発表もしていない発掘したての幼児のミイラを見せてもらった。2,000年近く前に埋葬された子供らしい。タクラマカン砂漠で発掘され、ラクダで道路まで慎重に運んだという。極度に乾燥した環境に守られ、つい先日に葬儀が行われたかのように美しい刺しゅうの服に遺体は包まれていた。小さな布製の靴がかわいらしい。幼子を失った親の痛切な思いが伝わってきた。
水稲をはぐくむオアシスも豊かだが、古代のミイラをいまも抱き、石油まで生み出す砂漠の懐も奥深い。
|
|