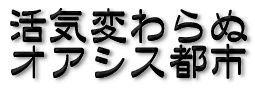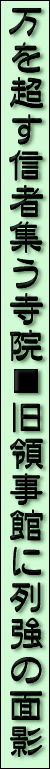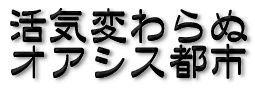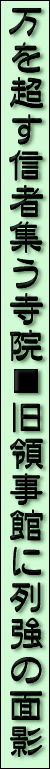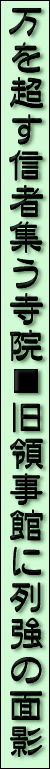 |
アジアの地図を広げ、中国領の西の果ての地名を探し出せば、そこがカシュガルだ。「喀什◆爾」。これでカシュガルと読む。最近では略して「喀什」と書く。
北京からは直線で約3,000キロ、新疆ウイグル自治区の中心ウルムチからでも1,000キロ離れている。いまでこそ飛行機を乗り継いで北京から2日で着くことができるが、さすがに“どん詰まり”に来たとの思いは強い。
そのカシュガルが最もにぎわうのは日曜の市場だが、もう一つ毎週金曜日に万余の人を集める場所があった。市中心部に位置するエイティガール寺院だ。500年以上の歴史を誇る新疆随一の大イスラム寺院である。
市場が俗的な欲求と物資の交換が行われる場とすれば、こちらは宗教エネルギーが総結集する聖域だ。礼拝に最も多くの信者が集まる金曜日の午後に訪ねてみた。
突然、私たちの周りに人だかりができた。「構内の礼拝風景を撮影したい」という私たちの要請を伝えるカシュガル地区外事弁公室の漢族の担当官。そんなことは認めないと突っぱねるウイグル族の管理人。二人が押し問答を始めたのだ。
人だかりはどんどん大きくなる。聖域でトラブルを起こすことは避けなければならない。私と北野カメラマンは現場を離れた。
幸いウイグル族の通訳ゼパールさん(24)が同行していた。事態収拾を彼に任せると、しばらくして妥協が成立した。構内に入るのは北野カメラマンとゼパールさんのみ、礼拝の信者を刺激しないよう撮影は後方から、という条件がついた。聖域に対するぶしつけな要求を恥じるとともに、この寺院の持つ重みをいや応なく知らされた。
寺院の周囲に門前市があった。衣食を中心にした日曜バザールとはちょっと性格が違う。主食のナン作りに使うめん棒を作る木地師、民族楽器屋、金細工師、じゅうたん売りらが軒を並べる。すべて手作りの世界だ。主役は職人。だれもが自信満々に手を動かし、堂々と自作を商う。一軒一軒ひやかすのに夢中になり、いつのまにか北野カメラマンともゼパールさんとも離れ離れになってしまった。
旧英国領事館は、エイティガール寺院のすぐ北にある「ジニワク賓館」の敷地内にあった。白壁に赤の縁取りがしゃれている。いまでも食堂として使われており、前庭のバラが満開だった。一方の旧ロシア領事館は、私たちが宿泊した「色満賓館」の敷地内にあった。こちらも高級な客室・会議室としてやはり利用されていた。
両国の領事館が置かれたのは、19世紀後半から今世紀初めにかけての帝国主義の時代だった。当時、新疆は清国の領土ではあったが、崩壊間近の清朝の統治能力は地におちていた。しばしば地方軍閥が政治・軍事の実権を握り、そこにロシア、英国が影響力を行使すべく領事館を置いたのだった。
地方政権抱き込みを図る虚々実々の駆け引きを展開しつつ、両領事館は辺境における文明の“浮島”の役割も演じる。しゅん険なパミールを越え、あるいは荒涼たるゴビ灘(たん)と砂漠を渡ってきた多くの外交官、探検家、そしてスパイたちがここでシャワーを浴び、洗練された料理で疲れをいやした。そのなかには、日本の大谷探検隊も含まれていたはずだ。
旧ロシア領事館をのぞきにいくと、建物の前にパキスタン警察の四輪駆動車が駐車していた。ウイグル族の女性服務員が「クンジェラブ峠の中パ合同管理委員会の会議が開かれているんです」と耳打ちしてくれた。
カシュガルの南約400キロのパミール高原にあるクンジェラブ峠は両国の国境線が走り、現在、外国人にも開放されている。峠を下れば仏像発祥の地ガンダーラに通じる。旧英国領事館のすぐわきはパキスタン行きの国際バスの発車駅になっていた。
中国の中原から見れば“どん詰まり”でも、視線を反対に転じれば西方、南方への玄関口である。かつて仏教が北伝し、探検家が行き来した峠道は、パキスタンとの良好な関係を背景に、現代のシルクロードとしていま新たに活況を呈している。
(注)◆は「口へん」に「葛」
|
|