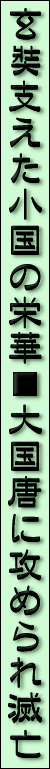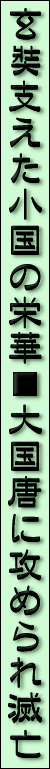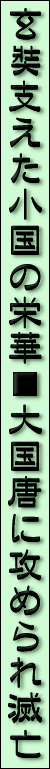 |
『西遊記』はお話だが、モデルになった唐の僧・玄奘(げんじょう)は仏教経典を手に入れるためのインドへの旅の途中、ここトルファンを本当に訪ねている。
玄奘が長安をたったのは西暦629年のことらしい。鎖国を破っての出発だったため、各地で妨害を受けた。
しかし、トルファンにあった高昌国の王・◆文泰(きくぶんたい)は敬けんな仏教徒だった。玄奘を温かく迎え、「高昌にとどまってほしい」と懇請する。玄奘は「目的地はインド。ご勘弁を」と断る。王は強制送還をほのめかして引き留めるが、玄奘は食を断って強く抵抗する。ついに王は、帰りに高昌国にとどまることを条件に出国を認め、金銀、絹など高価な餞別(せんべつ)を渡して送り出した。
この支援が大きな力になり、玄奘の約16年におよぶ取経の大旅行は成功を収める。恩義に報いるべく、玄奘は高昌に帰途立ち寄るつもりだったに違いない。が、なんということか、そのときには高昌国はなくなっていた。640年に唐の太宗によって滅ぼされていたのだ。
当時のアジアの超大国はむろん東の唐、そして高昌の西には唐ほどではないがトルコ系の有力な西突厥(にしとっけつ)があった。シルクロードの要衝という立場を生かし、二つの大勢力に適宜ゴマをすりながら生き延びていた高昌なのだが、唐の腹を読み誤り、西突厥との同盟を強めたところを唐に攻められた。いざ、唐が大軍を派遣してくれば、もう西突厥の腰は引ける。はかない同盟。小国の運命はいつの世も実に切ない。
火焔山のふもとに、いま高昌故城がある。高昌国の都の跡だ。入場門の前でウイグル族の若者たちが観光用ロバ車の客引きをしていた。客1人30元(400円強)が相場。懐から日本円の千円札を出し、「人民元に両替できないか」という男もいる。日本人の団体は春から秋にかけて毎日のようにやってくる。価値ある外貨を手にしたものの、地元の村では使いあぐねているらしい。
故城に入ると、住居や僧院の跡らしき土の遺構が無数に広がる。その間をロバ車が巡る。出会った団体は日本人ではなく、湖北省武漢市の労働者組織の12人だった。「西安、蘭州、敦煌を回ってきました。全行程12日です」と団長さん。いやはやシルクロードの黄金コースだ。改革・開放政策が本格的に動き出す前は、省外に出る観光旅行など夢物語だったという。中国人による国内観光がいま大ブームなのだ。いい時代になった。
自治区の区都ウルムチの美術学校の一団もいた。学生たちが遺構の上に駆け上っては歓声をあげる。その場所は日本でいえば国指定の重要な史跡だ。エッ、いいの? と思ったが、故城は周囲数キロにもおよぶ巨大な都跡。遺構ごとにさくなど作ってはいられない。大胆というか、おおらかというか。
火焔山をはさんで高昌故城の反対側の斜面にベゼクリク千仏洞がある。今世紀初頭、ここには「敦煌文書」で有名な英国のオーレル・スタインもフランスのポール・ペリオもやってきた。しかし、ここの“主役”はドイツのアルベルト・フォン・ルコックだ。
壁画をごっそりとベルリンに持ち帰った。悲劇はその一部が第二次世界大戦の空襲で灰じんに帰してしまったことだ。だから、ルコックの評判は中国でとくに悪い。石窟(せきくつ)の内部には「勒柯克(ルコック)窃画示図」、つまりルコックが壁画を「盗んだ」ようすを紹介するパネルが展示されていた。
このほか、トルファンには立派な仏塔が残る交河故城、大量の文書や塑像が出土したアスターナ遺跡など、かつての仏教の隆盛ぶりを伝える旧跡がめじろ押しだ。
しかし、いまトルファンに仏教はまったくといっていいほど存在しない。住民の大半を占めるウイグル族は、玄奘の同時代人マホメットがアジアの西の果てで開いたイスラム教を信仰している。小国の興亡とともに、宗教の変遷もまた劇的であった。
(注)◆は麹(こうじ)の異字で作りが麪の左側のもの
|
|