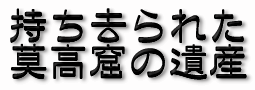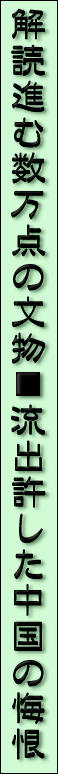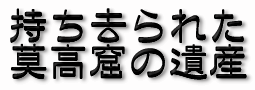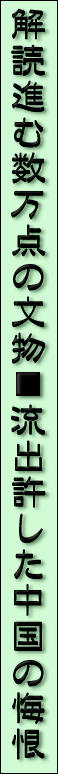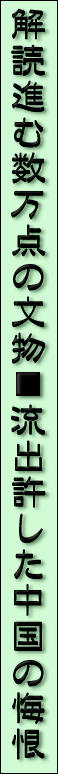 |
ロンドン市街の北部に移転新築されたばかりの大英図書館を訪ねると、中国を担当するフランシス・ウッド博士が一枚の仏画を見せてくれた。
「スタインが持ち帰った敦煌文書の一つです。10世紀のものです。こうした文書は、紙の材質や裏面の表記などを確認しやすいように透明なケースに入れて保管しています」
スタインが甘粛省敦煌の莫高窟はじめ、さらに辺境の新疆の古代遺跡などから持ち帰った文物は数万点におよぶ。考古学的資料は大英博物館、文書類は大英図書館が保管している。
あまりにも量が多いため、整理作業はいまなお続いている。同時に、世界各国の研究者の地道な文書解読によって、シルクロードの歴史の細部が年ごとに明らかになっているという。
中国奥地からはるばる運ばれてきた膨大なスタイン・コレクションを目の当たりにすると、中央アジア研究に生涯をささげ、アフガニスタンに客死したスタインの執念と情熱に圧倒される。背後には大英帝国の政治的な思惑があった。しかし、スタイン自身はこの宝の山を前に、なによりも一研究者として至福に浸ったことだろう。同じ興奮をペリオも味わったに違いない。
ウッド博士は、敦煌文書の国際的な研究事業「国際敦煌プロジェクト」の作業班にも案内してくれた。若い研究員が文書をホームページに載せる作業に追われていた。
博士は「敦煌文書はフランス、ドイツ、ロシア、日本などに分散しています。もちろん、中国にも残っています。一枚の文書がちぎれて分散している例もあります。ホームページに載せることで、各国の研究者がジグソーパズルのように突き合わせる作業にも取り組めます」と、新技術による敦煌学の新しい可能性を強調した。
率直に聞いた。スタインは略奪者だったのか、中国から返還要求は来ていないのか。「略奪者とは思いません。彼は中国から帰ると、文物を適正に保管し、直ちに詳細な報告書を発刊し、すべてを公開しました。返還問題は微妙なテーマですが、中国政府からの要求はありません」。文化大革命中に中国に留学した経験があるという博士は、慎重にそう答えた
。
中国に戻ろう。スタインやペリオ、大谷探検隊などについて、中国人研究者にあえて聞いてみた。
かつてスタインが発掘した楼蘭、ホータン周辺などの遺跡で現在調査を陣頭指揮している新疆文物考古研究所の于志勇副所長は「当時の中国側の保護が遅れていた事実は否定できません。が、あれほど多くの文物を国外に持っていった行為は、中国人としては容認しにくいものです」と答えた。
しかし、中国側がスタインらを一方的に略奪者呼ばわりしているわけではないことも、すぐにわかった。
タクラマカン砂漠に接する小さなオアシス都市での夕食のひとときだった。私の質問に現地の若い考古学者が言い切った。「スタインたちには感謝しています。中国人が守れなかった文物を丁寧に保管してくれたのですから。私たちの現在の研究にも役立っています」。これには、その発言が終わらないうちに、向かいの別の若手研究者から強い反論の声があがった。
和やかな会食の場が一転して凍りついた。長期間のシルクロード取材のなかでも最も気まずい場面だった。この話題を続ける勇気は私にはなく、お茶を濁すようにかれらに乾杯を促した。
世界に誇るべき文化財をなぜ列強に奪われなければならなかったのか。もし、奪われなかったとしても、大英図書館・博物館のようにしっかりとした保管ができただろうか−。
アヘン戦争で英国に敗れ、日清戦争では“小国”日本にも敗れた中国の知識人が抱き続けてきた屈辱、悔恨、いら立ち。学術の分野におけるその一端をシルクロードに見た思いがした。
|
 |
| 国際敦煌プロジェクトは大英図書館所蔵の敦煌文書を紹介するホームページを作成している。プロジェクトには中国の研究者も参加している |
|