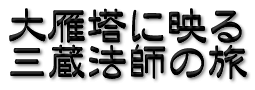
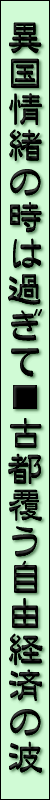 |
大雁塔は底部が正方形をした角すいの塔だ。斜塔になった原因は、塔の下の地下水が少なくなって地盤沈下が起きているためだという。 いったいに西安という都市は、北に黄河の支流、渭水(いすい)が流れてはいても、中国西北部に共通している内陸の乾燥気候のせいか飲料水が不足している。 だから建物の高さに制限がある。「あまり高層にしては少ない水を高いところまで揚げきれない」というのが中国人ガイド氏の説明だが、電力不足ということもあるかもしれない。 高層ビルが少ないせいもあって、中国西北地区随一、人口700万という大都市にもかかわらず、西安には北京や上海にはないひなびた古都の風情がある。 重々しい城壁の存在が大きいのだろう。高さ13メートル、幅12メートルというれんが造りの壁が、市中心部を周囲14キロにわたって長方形に取り巻いている。その完全に保存され、がっしりとした姿が頼もしい。城壁をすっかり取り除いたため景観が一変した北京とは、おもむきを異にする。 ただし、この城壁は明の時代のもの。唐代の城壁はその数倍も広かったが、十世紀の初め唐が滅んだ時、焼き払われた。唐代の面影を残すのは大雁塔などわずかな建物だけだ。 古都のにおいはあっても、かつての国際都市の雰囲気には乏しい。李白が「胡姫 素手もて招き 客を引いて金樽(きんそん)に酔わしむ」とうたったころ、酒家に青い目や金髪の女性が舞い、街の雑踏の中に黒い肌さえ光っていた時代は、遠くかなたに去った。 わずかに、西安に6万人いるという少数民族の回族の飲食店街がエキゾチシズムを誘ってくれる。めん類だと15元(1元は14円くらい)、50元もあれば羊肉を中心にしたフルコースをたっぷり食べられる。 郊外に出ると、小麦の収穫の真っ盛りだった。私たちが訪れたのは6月初旬。日本ではすでに死語になった「麦秋」という言葉が、ここで生きていた。 古びたコンバインが広い畑を走り回り、さびた脱穀機がけたたましい音を上げる。幹線道路には、刈り取りの賃仕事に出かける農民のグループがたむろしていた。子供のころに見た日本の昭和30年代の風景がよみがえったような感じだった。 街に戻り、飛田カメラマンが繁華街を歩くミニスカートの女性を撮っているのを街角で待っている間、ガイドのOさんが意表をつく質問をしてきた。 「あれ、何て言いますか。ロウ? そう、ロウで食べもの作る会社、知りませんか?」最初は何のことやら分からなかった。短いやり取りで、すぐに判明した。世界に比類ない日本固有の発明品、レストランが店頭に陳列するロウ細工のメニュー見本のことだった。Oさんは、それを作る日本の企業と提携して中国で製造販売する会社をつくり、お金もうけをしたいのだという。 西安の旅行社に勤める公務員ガイド、Oさんの年収は、日本の同年齢の男性の20分の1にも及ばないであろう。改革開放、自由経済の奔流の中で、この青年もまた人並みの野心を燃やしている。 私たち二人の周囲には、乗用車とホンダのオートバイと自転車の波が一見無秩序に渦巻いている。アメリカ資本のホテルビルの前には、日本で流行しているのと同じ高いヒールのサンダルと、今しがた小麦刈りを終えてきたかと思わせる、あかと土にまみれたズボンが行き交っている。 長安の春も、胡姫の歌もさらにはるかかなたに飛んでいってしまった。Oさんには申し訳ないが、ロウ細工の会社名は知らなかった。 |
|
||||||
|



