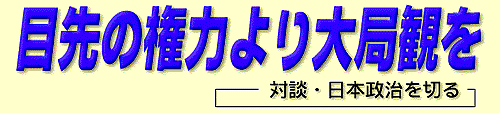
|
|---|
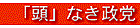
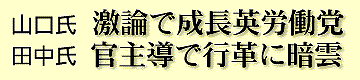
田中 今の政治をみると、四年間の連立政治が不毛だったと、つらいがそう総括せざるを得ない。冷戦、拡大経済の後の日本の政治を指し示す一番大きな宿題が解決されていません。私は自民党は「頭のない鯨」だと言っていますが、自民党自身がそのことに気付いていない。佐藤孝行さん(前総務庁長官)の入閣問題も、「頭」のあったかつての自民党ならなかったでしょう。佐藤さんではなく橋本竜太郎首相の問題です。今までの舞台装置を片付ける政治改革も成果を上げなかった。政局・選挙本位できた政治家・政党の責任です。「自民、非自民」「保・保、自社さ」の域を出ない。永田町は政治を解くカギを自分のものにしていません。 山口 総理大臣の重みが日本と英国で全然違います。英国は内閣・与党両方に首相が全責任を負います。組閣で意に沿わない人物を指名することは起こり得ません。橋本首相の場合、党は人ごと。党が議論したことをのまざるを得ない。 田中 今の自民党単独内閣は「ナポレオンの百日天下」です。世の中が変わったことを認識していない。行革がうまくいかないのは、民主導でなく行政主導の「官権行革」だからです。時代が大きく変わったことを認識したら、こうはなりません。 山口 日本は与党が巨大な圧力集団みたいに振る舞い、行革の議論をひっくり返す。与党がどういう方向性をとるか、広い視野で議論する場がない。あるのは部会レベルの議論 。それを束ねて「ここは痛みを乗り越えて」というイニシアチブを取る人がいません。 田中 「自民党は頭がない」と言ったが、官僚組織が「頭」の役割をしている。官僚は責任の主体たり得ません。問題は野党も「頭のないアジやサバ」になっていることです。力が先にあってその後で価値目標を据える政治は成功しません。数を集めることが目的化された民主党の失敗もそこにある。政局遊びは政治の末期現象です。 山口 政権構想がないところで数を合わせても、政権の選択肢となり得ません。民主党 は、公共事業にしても農業政策にしても北海道の旧社民党系の人たちと、都府県の議員と の食い違いが大きい。具体的課題に方向性を出さず、イメージだけで何かをやろうとして も、国民はそれを信頼するほど愚かではありません。 田中 政策決定の主体を官僚組織から国民に移す期待は民主党にまだ捨て難いが、民主党は仕組みの話しかしない。日米防衛協力のための指針(ガイドライン)、国連安保理常任理事国入り、財政と金融の分離など、具体的な問題に影響力がまったく出てきません。「賛否両論あって差し障りがある」といって具体的に動かないのでは、何のために政党をつくっているのか。個別の政策課題では昔の自民党や社会党の方がはるかに明快だった。そうした五五年体制を乗り越えるには、単なる政局論ではダメです。一人一人の政治基盤、閲歴が引きずられていると民主、リベラルとか抽象的なものしか出ません。具体的な目の前の重要政策に発言できないで何の流れが生まれますか。有権者側はいつでも支援する用意があるのに白けているのは、そういうことだと思います。 山口 やはり「頭」の確かな英国の政党政治がうらやましい。労働党はサッチャー全盛期に壊滅的に敗北し、どうすれば国民から支持を得られるかちゃんと考えました。綱領改正、福祉国家の根本的改革とか党の存在意義にかかわる問題も激しい論争をして新しい方向をつくる。政党が国民から信頼される手掛かりは、身内にどれだけ厳しいことが言えるかです。昔のようなストばかりやる労組はダメだ、経済構造が変わる時にどう競争力をつけるか課題を共有する労組たれと、一昔前なら考えられないことを打ち出し、そのあつれきを乗り越えて国民政党になれる。「連合が何か言ってくる」とか、大スポンサーを意識した形の野党結集ではインパクトがありません。ある部分では、働く人たちの利益を代表しながら既得権をどこまで切れるか、そこを乗り越えないと宮城で示された民意はついてきません。 田中 終戦直後、苦しい戦争を勝利に導いたチャーチルからアトリーに首相が代わった。その流れで、衰弱した英国に新たなシステムをつくった保守党があぐらをかき始めたら政権が交代した。有権者が違います。成果を上げたからそのごほうびにしばらくやらせてもらうという話は通用しない。有権者のクールな判断が示されるとの思いを強くしました。 山口 特定の団体の号令で動くというのは英国でも少なくなり、組織されていない人たちの票をどうやって掘り起こすかに知恵を絞っています。労働党が勝てたのも、労組といい意味の緊張感をつくり出し、ある部分で社会的公正とか彼らの価値を打ち出した。そこのメリハリがうまく描けました。 田中 労組が政党を支持するのはいいが、労組が変わらなければ政党も変わらない。英国の労組はどうなっていますか。 山口 かなり変わりました。雇用の構造も伝統的な炭坑や二次産業から第三次産業にシフトしてきた。組合自体ボス支配を排する組合内民主主義みたいな形、ある意味でサッチ ャリズムの遺産ですが、一般組合員の投票で方針を決定する方向に変わってきています。 |