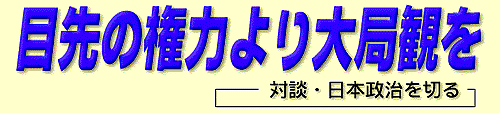
|
|---|

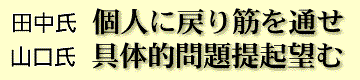
山口 個人が戦う首長選挙は主張、行動がまだ見える。政党は人間の肉声、考えが伝わってきません。国民の期待を取り戻すには、見える場で党内論争をやらないとダメです。郵政事業民営化の自民党内論争も政治家の信念ではなく、特定郵便局長会や官僚に言われて論争する。 田中 自民党は古くても五十年の風雪に耐えた家です。それを壊して更地にしない限り、新しい家が用意されていなければ、とりあえず古い家に住んでいようという気になってしまいます。北海道では連合が呼びかけて民主、新進、公明が一緒に選挙協力を探る動きがあるようだが、もうそういう話はやめてもらいたい。この四年間に何を学んだのか。政治家は個人に戻るべきです。党との緊張関係の中で、自分はこれをやるという筋を通すところからしか信頼は回復しません。 山口 はっきりしているのは、利権の見返りに票を束ねる今までのやり方は破たんするということです。大局観をもって政策・政権構想を発信していればチャンスは来る。目先の権力を維持するのか、三−四年先のチャンスをつかむのかが、政権戦略の違いになります。 田中 政治家には二種類ある。地位を得てから志を用意する人と、志があって地位を得る人。今は前者が多い。だから地位が危うくなると志を変えるのです。日本政治の世襲体制に本質的な問題が投げ掛けられている。政治の外にいる人材が中に入る形でないとこれは乗り越えられない。英米にはそのような代謝機能が制度自体に含まれているが、日本では間に合わせの旗を立てるだけ。装いが新しく見えるだけなのです。政治をやってから元の職場に戻る復職規定があっていい。「すべてをなげうつ」などと簡単に言う人は信用できません。現実は、たまたま政治家になる基盤を持つ人しか選挙に出られない。 山口 政党政治の中で政策対立の軸が立てにくくなってきたとの議論は、欧州でも強い。しかしそれは政治家の怠慢です。かつてのようなイデオロギー対立ではないとしても、具体的問題を議論すれば対立は出る。例えば二酸化炭素(CO2)の排出基準は、数字ではなく価値観の問題です。われわれ自身の生活、将来への姿勢が問われてくる。これこそ政治家自身が語るべきテーマのはずです。 田中 こういう事についてものを言えない政治家は何を言ってもだめだ。政府に厳しく迫る問題があるにもかかわらず、やったらこういうマイナスあるからとしのいでいく。 山口 対人地雷の問題もしかり。政治家は国会で議論する機会があるのです。 田中 政治家は消費者が痛みを引き受けないとの前提でものを言うが、政治家を信頼さえすれば、我慢する姿勢も持っています。有権者が政治に求めるものは、日本と英国で違いますか。 山口 英国では選挙そのものが政党本位です。どの政党の政策が一番いいかで判断する。候補者もいわゆる落下傘、故郷でもなんでもない選挙区に立候補する例が多い。政党の地方組織が候補者を公募選考するのですそ野が広く、教師や女性など政治に関心ある人がどんどん競争に入ってくる。議員もどんどん法案を出して公約は必ず任期中に実現しようとする。 田中 そこが日本と決定的に違いますね。 山口 政策とポリシーは違うんです。日本では政策とは願望の羅列だ。ポリシーには裏付けがある。新しいことなら財源や国民負担をどうするか、そこを詰めて議論しています。 田中 政党が責任主体になるというのは、僕の言う「民権政治」です。野党の民主党は具体的な問題できちんと答えを示してほしいですね。 山口 きちっと詰めてものを考えていない感じがします。利益誘導政治を超えるものを示せていません。CO2を削減するために、マイカーの使用をこれくらいまで抑えるなど、生活がどれくらい変わるかまで含めて問題提起してほしい。本物の政策に皆飢えています。もう一つ、今の政治に必要なのは、役所が選挙を手伝わず、かつ手伝わせないことだと思うのです。 田中 同感です。行政の世話なっている政治家に行政の監視はできません。 山口 役所に選挙を手伝ってもらった人が、何かを切れるわけがない。郵政事業の問題が典型です。 田中 小泉純一郎さん(厚相)は郵便事業への民間参入と郵貯民営化の方向が示されることの二つを主張している。小泉さんには政治家としてこの主張の筋を通してほしいと思う。彼は、政局より自分の志を優先できる数少ない政治家と思われているところに信頼がある。土壇場で、内閣がおかしくなるとかYKKがどうだとか、そういううんざりするようなことで矛を収めないでほしい。 山口 まともな行革論議をしている唯一の論客として小泉さんには持論を通してほしい。役人が選挙の世話をして政治家を動かしていくという自民党の議論の構造自体が行革の対象だ。彼が孤塁を守って正論を貫けば世論は付いていくと思う。 |