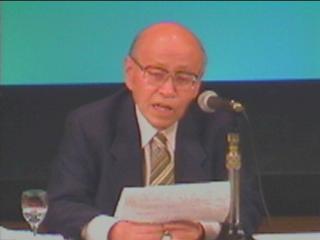
地域の自立−私の現場体験から−
株式会社整理回収機構社長・弁護士 中坊 公平氏
整理回収機構社長で弁護士の中坊公平氏の特別講演を行います。弁護士としてご活躍の中坊氏は、ヒ素ミルク事件被害者弁護、豊田商事の破産管財人などの活動を経て90年から2年間、日弁連会長、住宅金融債権管理機構社長を務めて、この4月からは整理回収機構社長に就任されています。
それでは中坊さんよろしくお願いします。
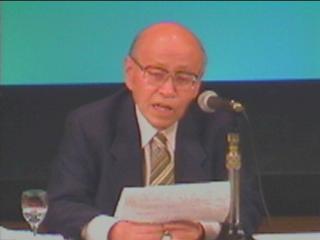
● はじめに
まず、本日のテーマである「地域の自立」を考えるとき、当然ですが一番大きい問題は地方財政の危機であります。平成元年に80兆あった財政赤字が、平成10年には2倍の160兆になり、現在では元利金の返済が予算の20%以上となる自治体が全国の6割を占めるまでにいたってます。
また地方交付税中心の地方財政は、中央中心の行政という問題にもつながっております。
しかしながら、本日の講演では「地域の自立」を「私自身の自立」という視点から考えてみたいと思います。
● 私の自立
まず私は、例えば日本という国やあるいは何か特定の集団において、罪であるとか無実などがあるのではなく、すべては一人一人の個人の問題だと考えています。同じように、「地域の自立」というテーマにおいても、一人一人の自立から考えるべきものだと思います。
私は子供の頃から学校では落ちこぼれ組みで、旧制の中学、高等学校にも失敗しながらそれでもなんとか昭和32年に弁護士となり、昭和34年に独立しました。ところが、独立したその年の暮れにお金の計算をしてみるとお金が全然無いわけで、そのとき自立していない自分にはじめて気付かされました。
その後、ある会社が和議を申請してそのとりまとめの仕事を私がすることになりました。そこで現場に入ってみると工場は穴ひとつ開けるにもきちんと水平を取っていないようなひどい状態で、私は工場長のようにいろいろ指示を出すことまでしたわけです。結果、何とか立ち直らせることが出来たのですが、そうしたら今度はそれを見ていた債権者の方々から仕事をいただくようになったんです。その時、私はやっと自立できたのかなと自覚した経験を持っています。
私は「自立する」ということは現場を知るということだと思っています。現場を知ることの効用は3つあると思います。1つは物事の本質は現場にしか存在しない、だから現場に徹した思考が必要であるということ。2つめは物事を誰かに説得するためには、その現場の実際に即して語らなければならないということ。3つめはどうなるかわからない未来に向かって進んでいくためには、現場の体験の中から出てくる直感が重要だということです。
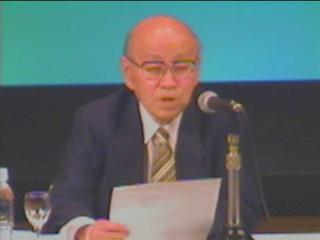
● パブリックを考える、行動する
しかしまたある時期、ヒ素ミルク事件で多くの被害者の方々と会う中で、ようやく自立したと思っていた自分に再び疑問を持つようになりました。10日か20日くらいしかヒ素ミルクを飲んでいないのに被害者となってしまった方々に対して、本当に後遺症がそんなに残るものかと疑問を持ったんです。それは「現場を知る」という原則から離れてしまっている自分に対して出た疑問でもありました。
そこで私は被害者の家に泊まって直接触れ合うことで明らかにしようと思いました。そして1年あまりに渡って土日に被害者宅を訪ねては泊まり歩くという活動をしました。それで分かったことは、被害者の親は森永に対する恨みを語るわけではなく、ヒ素ミルクの入ったミルクを飲ませたことに対する後悔で自分ばかりを責めていた事実です。被害者の親にとって本当の意味での救済というものはない、自分を責めることしかできなかったわけです。
その時に私は裁判により解決できることの限界、司法の限界を知りました。そして、それ以来ものごとを根本的に考えるようになったと思っております。
私は今、整理回収機構の社長を務めていますが、この機構が関係する法律ではなんの罪もない国民が、(公的資金という枠組みによる税支出を通じて)さらに2次負担を負うことになっていました。そこで私は何とか国民による2次負担が出ないようにやろうと取り組んでいます。
国を良くするということは地方を良くするということです。私たちは現在、「公(おおやけ)」という言葉を「官」と読み違えてはいないでしょうか。戦争で「官」や「国」という言葉が嫌いになった反動で、戦後50年の個人主義の中であまりにもエゴの強い社会を作ってしまったのではないでしょうか。
タテの「公」よりもヨコの「公」を大切にがんばっていきましょう。