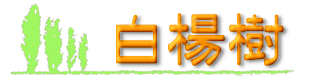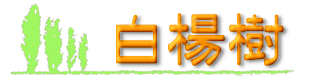|
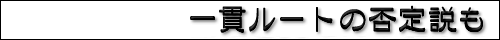
これまでシルクロードについて、どの本にも書かれているのと同様な説明をしてきたわけだが、学術的には、シルクロードなど「ない」という主張をする学者もいる。
その説によれば、「長安からローマまで」などというような、まるで高速道路のように一貫したルートなど、歴史的に存在したためしはないし、またそんな長距離を単独の隊商が往来していたということもありえない。
そもそもユーラシアの交易路というものは、あるオアシスから次のオアシスへ、このキャラバン・サライ(隊商宿)からあのキャラバン・サライへというように、いわばこま切れの通商路がつなぎあわさったものが結果として東西を結んでいるのであって、むしろわれわれはそれぞれの自然環境や風土に根ざした各地の歴史、生活、文化をこそ知らねばならず、蜃気楼(しんきろう)のごとき「シルクロードの全体像」など追うべきではないというのである。
この考え方には一理あり、現に最新の内陸アジア研究の大部分はこうした地域研究の観点からなされていて、そこでは文献調査とフィールド・ワーク、それに考古発掘が欠かせない。また「シルクロード」という用語自体、十九世紀後半、ドイツ人地理学者リヒトホーフェンが初めて使ったもので、その意味ではけっして古い概念ではないのである。
ただしこのことばが、「道」の本質を一言でとらえ得ていることも、また確かだろう。
(濱田英作・埼玉女子短大教授)
|