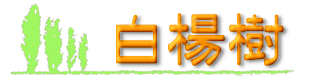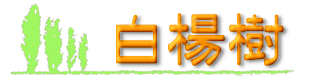|

ラクダの背に揺られて、はるばる長安ヘやってきたソグド人隊商は、三彩俑に見られるように、とんがり帽子をかぶっていた。その形を見ると、上端は前方に傾き、ときには折れて丸まっているようにすら見える。また、両耳と首筋とをおおう部分が、それぞれ長く垂れているのが特徴だ。
この帽子は、元来はスキタイや匈奴(きょうど)といった、遊牧民の被(かぶ)り物だったようだ。またバルカン半島のトラキア人や、小アジアのフリュギア人もこれを使用しており、そのためヨーロッパではフリジア帽として知られている。
目を転じて東方では、五胡十六国から南北朝にかけての北方民族南下の時期に、どうやらこの帽子は中国服の一部として取り入れられたのではないかと、私は見ている。
それが◆頭(ぼくとう)というもので、唐の章懐太子李賢の墓の壁画に描かれている儀じょう隊や、わが国の聖徳太子がつけている冠だ。
あの形をよく見ると、フリジア帽の両耳の部分と首筋の部分とを持ち上げて、髷(まげ)の根元で固定している(両耳だけの場合もある)。この◆頭を考案したのが、鮮卑族の王朝である北周の武帝だというのも、いまの推測を支えるものだ。
フリジア帽は自由の象徴とされ、フランスをあらわす女神マリアンヌはこれをかぶっているし、日本でも◆頭は束帯の冠に発展しており、その影響の大きさには、シルクロードの諸民族も、もって瞑(めい)すべきだろう。
(濱田英作・埼玉女子短大教授)
(注)◆は「僕」の「にんべん」が「巾」
|