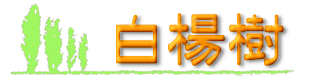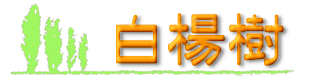|
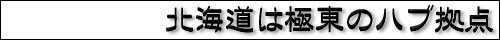
北海道にかかわりの深いシルクロードといえば、かつて北海道新聞でも特集された、「蝦夷錦の道」と、「コンブ・ロード」だ。
蝦夷錦は、清朝政府が沿海地方の諸民族に下賜した官服が、交易品としてアイヌの首長たちの手に渡ったもので、それがまた松前藩を通じて和人に知られた。
この服はもちろん絹織物で仕立てられているから、蝦夷錦の道はまさに「シルク」ロードである。しかもこの道は中国東北を通るから、「草原の道」に接続するともいえよう。
蝦夷地と呼ばれたころの北海道が、ユーラシア経済の一環を成していた、目に見える証拠だ。
一方、コンブ・ロードは、北前船に積み込まれた昆布がたどった道だ。昆布は京や上方では必需品だが、これがさらに九州から、当時薩摩の支配を受けていた琉球、つまり沖縄へともたらされた。
これだけならまだ日本の影響下の地域だけの話だが、沖縄の昆布は、さらにそこから朝貢品として中国へ渡っていったのであり、その面からは、コンブ・ロードもやはり「海の道」の一部を形成した、シルクロードの一環だといえる。
昨今、環日本海文化圏がクローズアップされ、各地で地域振興とからめた北前船文化の見直しが盛んだが、もっと広く見れば、かつての北海道はまさに、極東シルクロードの「ハブ拠点」だったのである。
(濱田英作 埼玉女子短大教授)
|